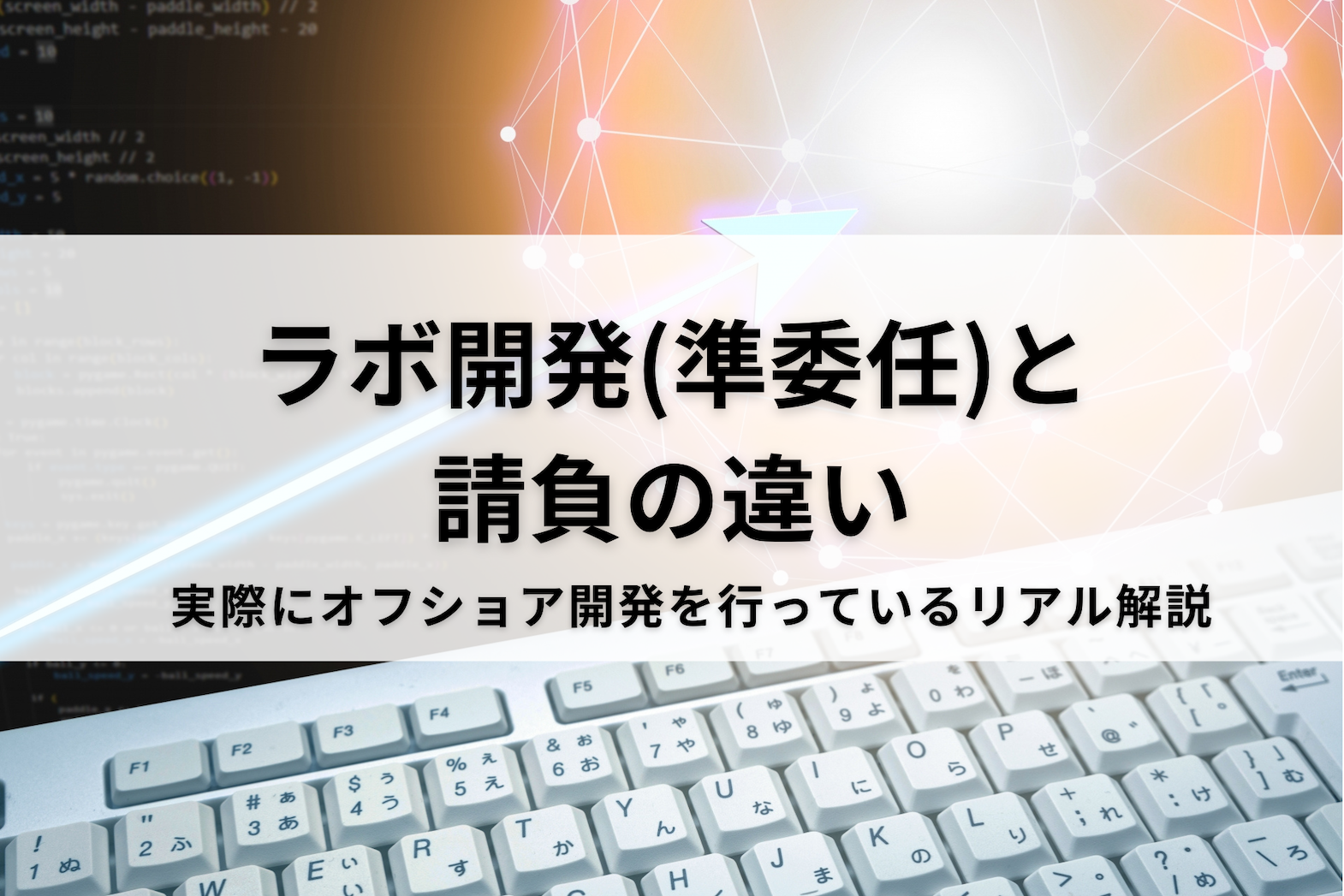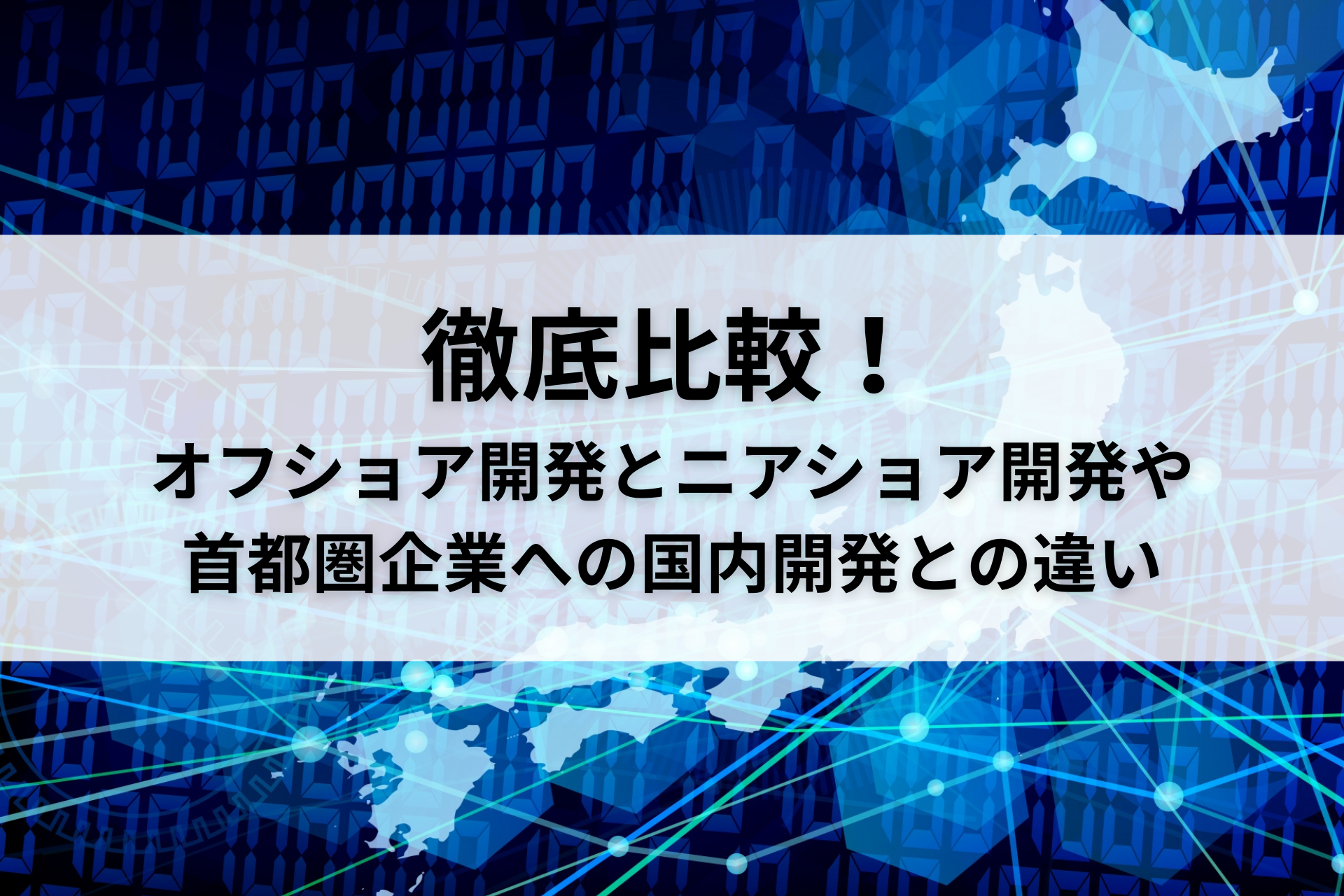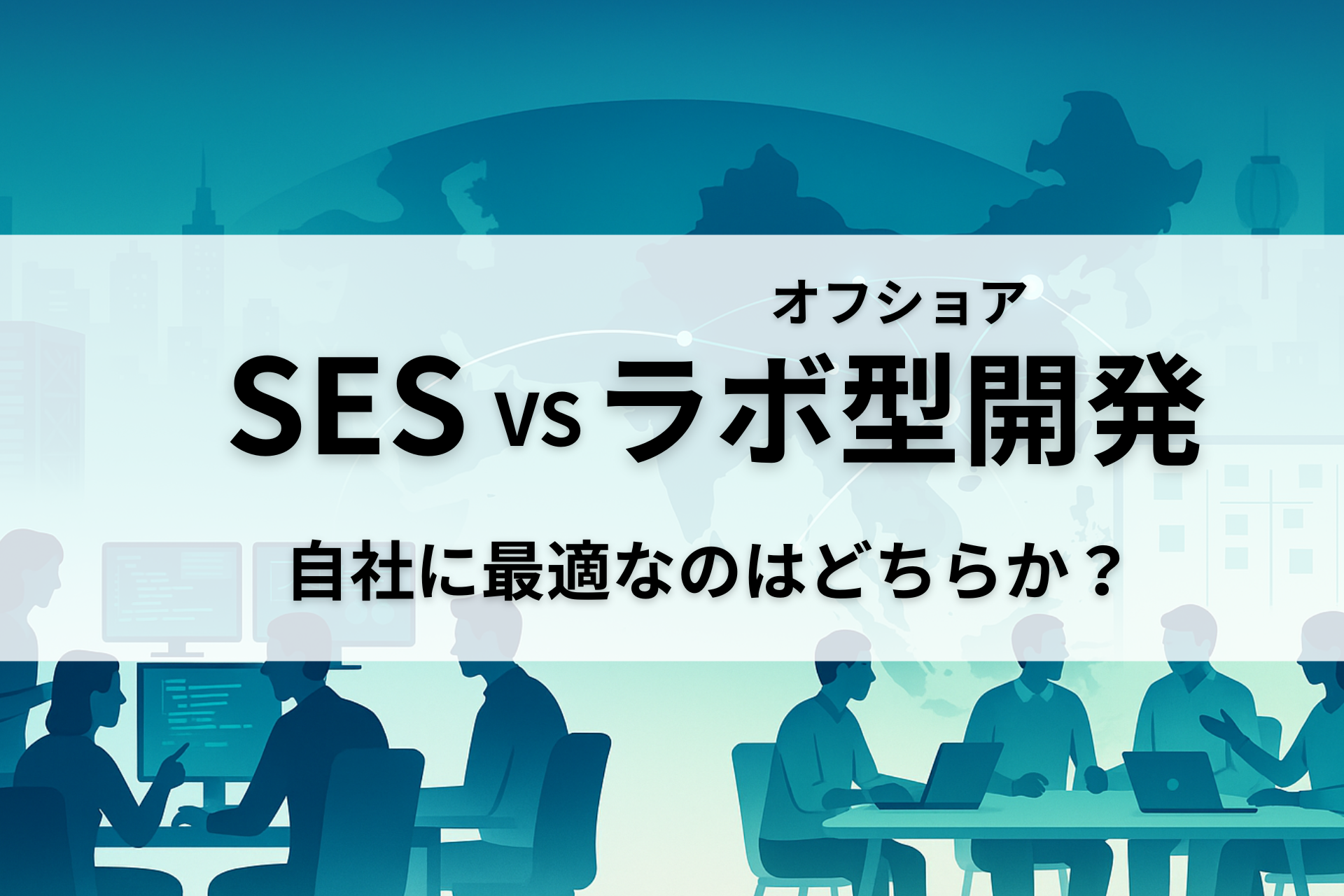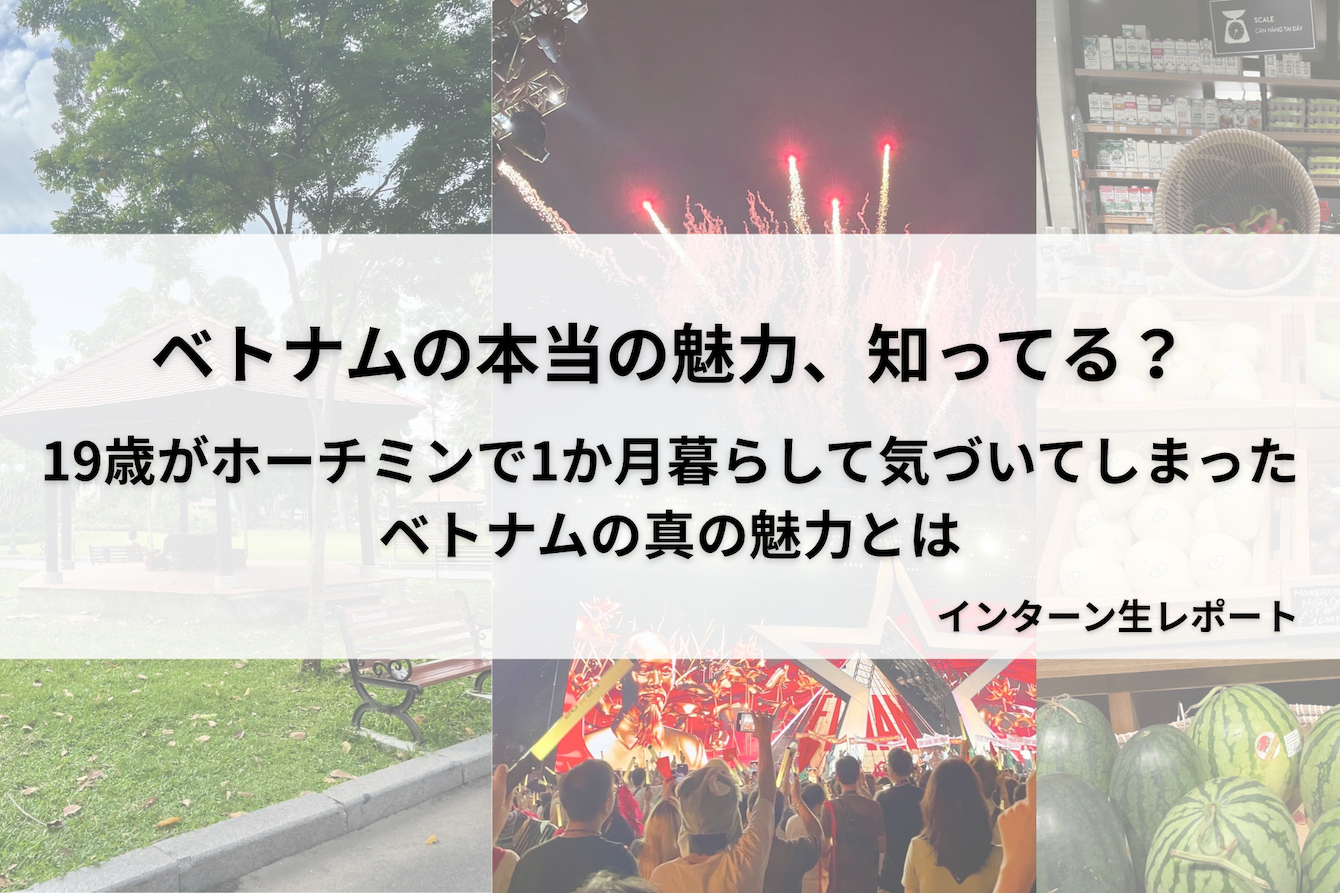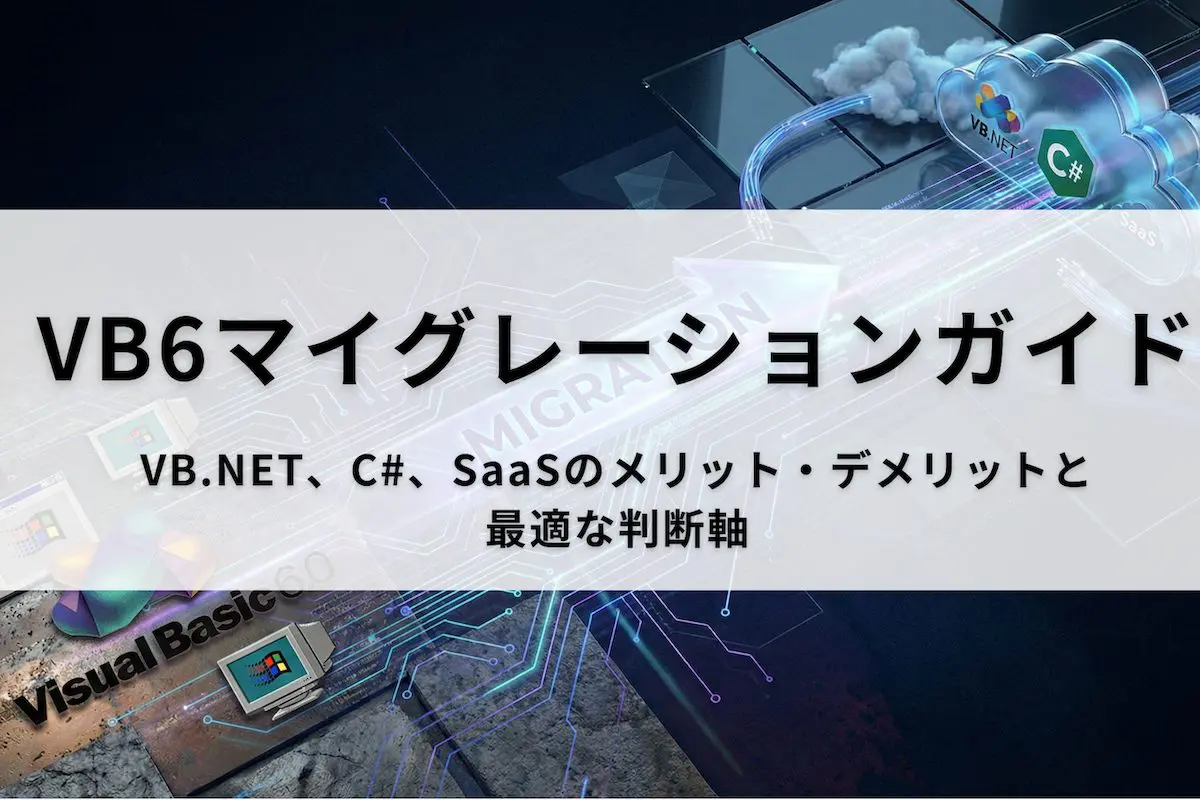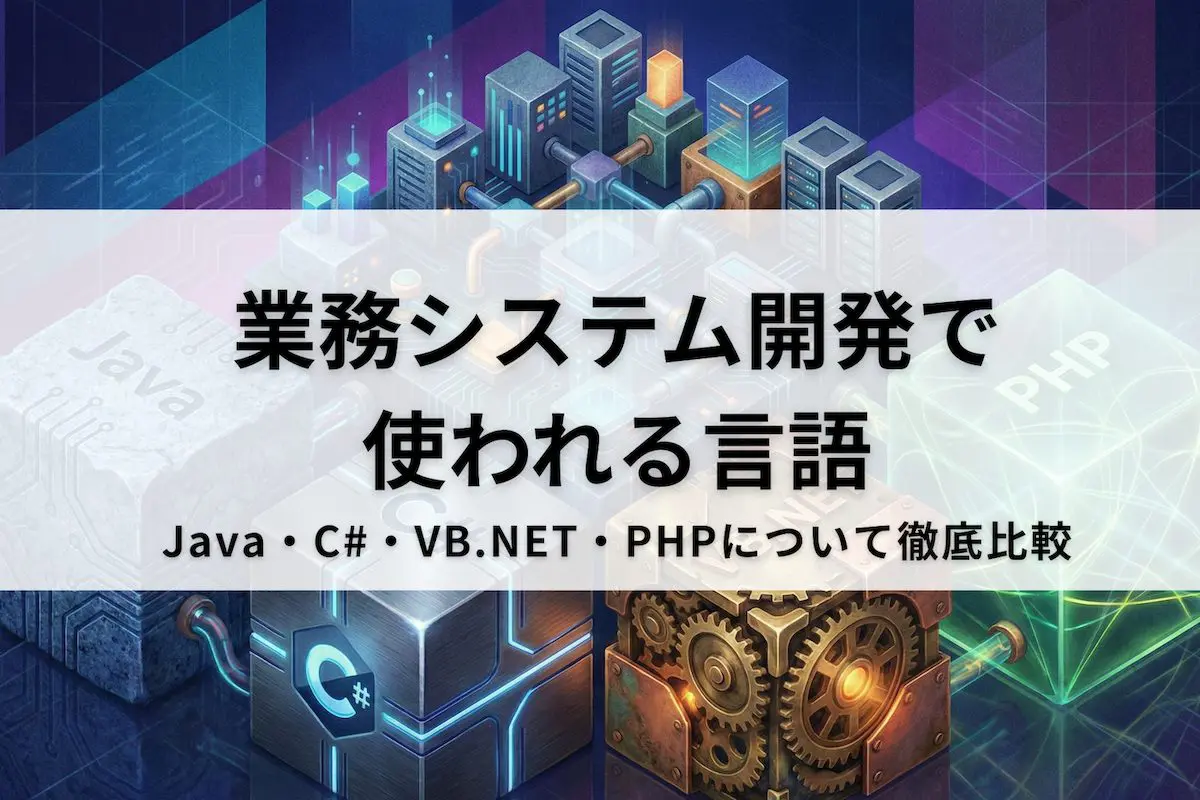2025/08/18
Share
オフショア開発とは?メリット・デメリット・成功のコツを徹底解説
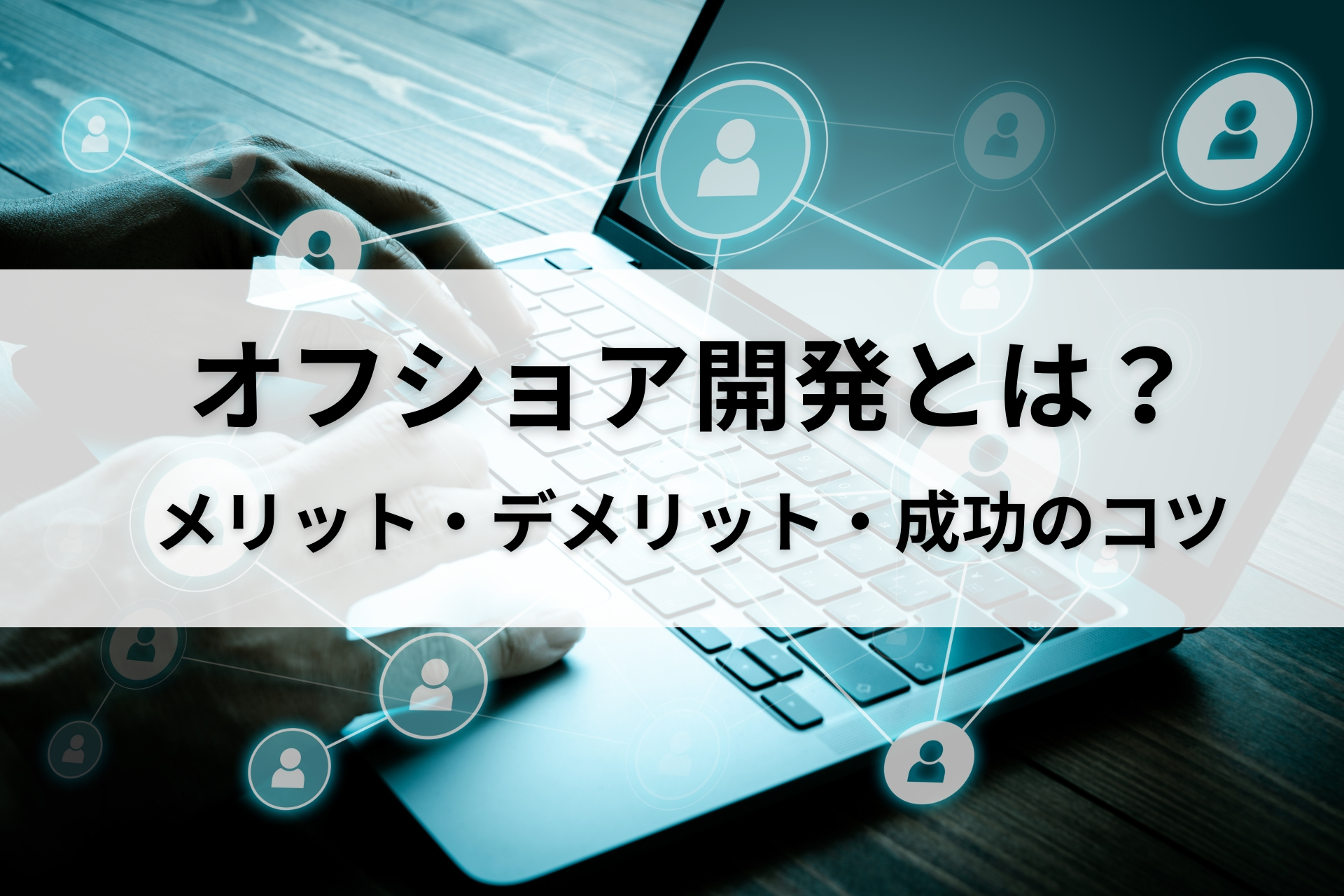
目次
コストを抑えながら、優秀な開発リソースを確保したい——。そんな課題を抱える企業が注目しているのが「オフショア開発」です。
かつては品質やマネジメントに課題があると言われたオフショア開発も、近年はパートナー選定や運用体制の工夫により、十分に活用できる選択肢となっています。
この記事では、オフショア開発の基礎から、メリット・デメリット、成功のためのポイントまで、決裁権を持つマネジメント層の方に向けてわかりやすく解説します。
オフショア開発とは?
オフショア開発とは、自社のソフトウェア開発業務を海外の企業や開発拠点に委託することを指します。
開発拠点としては、ベトナムやインド、フィリピンなど人件費が比較的安く、優秀なIT人材が豊富な国々が主流です。
日本国内での開発と比べてコストを抑えられるほか、リソース不足を補える点から、多くの企業が検討対象としています。
オフショア開発を選ぶ主な理由・背景
オフショア開発がここ数年で広く普及してきた背景には、以下のような理由があります。
深刻な国内エンジニア不足
経済産業省の試算では、IT人材の不足数は2030年に最大79万人に達すると言われています。
とくに中堅〜大手企業が複雑な開発を進めようとすると、必要なスキルや人数を国内だけで確保するのは困難です。
開発コストの高騰
エンジニアの人件費が高騰する中で、開発費全体を抑えながら品質を保つための手段として、オフショアは現実的な選択肢となっています。
国内パートナーのリソース枯渇
近年、国内の開発会社に相談しても「リソースが空いていない」「3ヶ月待ち」といった状況が珍しくありません。
案件のタイミングが合わず、チャンスを逃すことを避けるため、オフショアパートナーを“第二の開発ライン”として確保しておく企業も増えています。
オフショア開発の主なメリット
オフショア開発には、単なる「コスト削減」以上の魅力があります。
近年では、ビジネスのスピードや技術革新に追いつくために、戦略的にオフショアを活用する企業も増えています。ここでは主なメリットを4つに絞ってご紹介します。
コスト削減
もっともわかりやすく、かつ実感しやすいのがコスト面でのメリットです。
日本国内と比べて物価・人件費の安い国(ベトナム、フィリピン、インドなど)に開発業務を委託することで、同じ品質でも約半分〜3分の1の開発コストで収まることも珍しくありません。
また、固定費となる自社内の人員を増やすよりも、必要なときに必要な分だけ外部リソースを活用することで、開発投資の柔軟性を確保できる点も企業にとっては大きな利点です。
優秀な人材の確保
「この技術がわかるエンジニアが社内にいない」「国内のパートナーに依頼しても空いていない」——そんなとき、オフショア開発は力強い選択肢になります。
インドやベトナムでは、数学・工学分野に優れた教育水準を持つエンジニアが多く、AI、ブロックチェーン、クラウドネイティブ開発などの最先端領域にも対応可能な人材と出会える可能性があります。
特にベトナムは、日本語学習者数が年々増えており、「日本向け案件」に慣れたエンジニアやBrSE(ブリッジSE)も多く在籍しています。
長期的な開発体制をスケーラブルに維持できる
特定のプロジェクトだけでなく、継続的に進化が求められるプロダクト開発においては、リソースの波に応じて柔軟に体制を調整できることが重要です。
オフショア開発は、長期的な視点でチーム拡大・縮小がしやすく、コストを抑えながら開発体制を維持する手段として有効です。
社内リソースの集中と最適化ができる
オフショアを活用することで、社内の開発メンバーを企画や設計、プロダクトマネジメントといった上流工程に集中させることが可能になります。
開発やテストといった工数の多い作業を外部化することで、組織全体の生産性と専門性が高まるという効果が得られます。
オフショア開発のデメリットとリスク
オフショア開発は多くのメリットがある一方で、注意すべき特有のリスクや課題も存在します。
とくに初めて導入する企業にとっては、「国内開発とは勝手が違う」と感じる場面も少なくありません。ここでは、発注側が事前に把握しておくべき代表的なリスクを3点ご紹介します。
コミュニケーションの壁
もっともよく聞かれるのが、言語・文化の違いによるコミュニケーションギャップです。
たとえば「仕様を伝えたつもりでも意図が正確に伝わっていなかった」「報告内容が抽象的すぎて判断できない」「指示の優先順位が伝わっていない」といった課題は、実際の現場でも起こり得ます。
また、国によってはYESと言いながら内心では理解していなかったり、曖昧な指示をそのまま実装してしまったりするケースもあるため、“あいまいさ”に対する許容度が異なることを前提に設計することが重要です。
この課題に対処するには、ブリッジSEの配置や定例ミーティングの設計、成果物のレビュー体制など、“伝えたつもり”を防ぐ仕組み化がカギとなります。
品質管理の難しさ
開発チームが遠隔地にいるため、国内開発に比べてリアルタイムでの進捗把握やコードレビューが難しくなるという点も注意が必要です。
また、「何をもって品質とするのか」という認識がチーム間でズレていると、リリース直前になって手戻りが発生するといった事態にもつながりかねません。
このようなリスクを避けるためには、開発初期の段階で以下を明確にしておくことが重要です。
・コーディング規約やレビュー基準の共有
・テスト仕様・受け入れ条件の明文化
・KPIや品質指標(バグ件数、レビュー通過率など)の設定
「品質は指示でなく設計で担保する」という視点が、オフショア活用ではより一層求められます。
セキュリティ・知的財産リスク
開発拠点が海外にあることで、ソースコードや設計情報、個人情報などの取り扱いに対する不安を感じる企業も少なくありません。
とくに金融・医療・製造業など、機密性の高い業務を扱う業界では、外部委託にあたって社内規定や法務との調整が必要不可欠です。
以下のような観点で、事前に対策を講じておくと安心です:
・NDA(秘密保持契約)の締結と内容確認
・サーバーやコード管理環境のアクセス権限設定
・開発拠点での情報セキュリティ対策(ISO27001取得など)
・各国の法律や知的財産保護制度の確認
オフショアだからといって無条件にリスクが高いわけではありませんが、国内以上に「契約」「ルール」「管理体制」が明文化されていることが、信頼できるパートナーの条件になります。
オフショア開発を成功させるためのコツ

オフショア開発の成否は、技術力だけでなく「準備」と「運用体制の工夫」に大きく左右されます。
単なるコスト削減ではなく、長期的な開発パートナーとして成果を最大化するには、以下のポイントを意識した設計が重要です。
ベンダー選定の見極め
オフショア開発で最も重要なのは、「誰と組むか」です。
「価格が安いから」「人員が多いから」という理由だけで選ぶと、後々トラブルになるケースも少なくありません。
たとえば、過去に日本向けの開発経験があるか、技術面だけでなく課題対応や改善提案など“思考力”を伴う対応ができるか、プロジェクト管理体制は整っているかなど、複数の観点から総合的に判断することが求められます。
また、実際にトライアルプロジェクトを通して品質や対応力を確かめてから本契約に進む“段階的導入”も有効です。
プロジェクト管理の工夫
物理的な距離があるからこそ、「現地任せ」「丸投げ」では成功しません。
発注側にも適切な管理体制が求められます。
具体的には、要件を事前に丁寧に整理・共有したうえで、開発中も定期的な進捗確認や課題のすり合わせを行う仕組みを設けることが重要です。
たとえば、以下のような体制が効果的です。
・開発前に仕様や設計方針を明文化して共有
・毎週または隔週で定例の進捗確認ミーティングを実施
・チャットやタスク管理ツールを活用し、課題や対応状況を“見える化”
・レビューのルールやフィードバックの流れをあらかじめ決めておく
「進めながら調整する」ではなく、「進める前に共通認識をつくる」というスタンスが、オフショア開発の成功確率を大きく高めます。
コミュニケーションの意識
オフショア開発では、「言った・言わない」「伝わったつもりだった」が原因で、信頼関係にヒビが入ることも少なくありません。だからこそ、単なる情報のやりとりにとどまらない、
“人と人”の関係性を意識したコミュニケーション設計が欠かせません。
とくに意識したいのは以下のような点です。
・メールやチャットだけで済ませず、顔の見える打ち合わせを定期的に行う
・一方通行の指示ではなく、相手の理解度や提案を引き出す双方向の対話を意識する
・スモールトークや雑談を交え、文化や価値観の違いへの理解を深める
・感謝や労いの言葉を伝え、心理的安全性を育む
こうした「ちょっとした気配り」の積み重ねが、技術や体制だけでは補えない“チームとしての一体感”につながります。
特に長期プロジェクトや継続的な協業を目指す場合、最終的な成果にも大きな差が生まれるポイントです。
よくある失敗とその回避策
オフショア開発には大きな可能性がありますが、「安く発注できるから」と気軽に始めてしまうと、かえって高くつくというケースも少なくありません。
ここでは、現場でよく見られる失敗パターンと、それを回避するための具体策を紹介します。
期待値のズレ
最も典型的な失敗が、「丸投げすればやってくれるだろう」「自分たちの意図を汲んでくれるはずだ」といった認識のズレです。
これは、仕様書に書かれていない“暗黙の前提”や、“当たり前”が共有されていないことで起こります。
たとえば「急ぎの案件」とだけ伝えても、どこまでが優先で、何を後回しにしていいのかを相手が判断できるとは限りません。
こうしたズレを防ぐには、開発前の段階で以下を徹底することが重要です:
・要件・背景・目的をセットで伝える
・「できれば」や「いい感じに」といった曖昧な表現を避ける
・想定するアウトプット例や画面イメージを共有する
共通認識は自然に生まれません。丁寧に“作りに行く”ことが大切です。
管理不足によるプロジェクト迷走
進捗報告が来ない、スケジュールがずれ込んでも気づけない、誰が何をやっているかわからない——。こうした状態に陥ると、プロジェクトは迷走しがちです。
国内での開発と異なり、オフショアでは物理的・心理的距離があるぶん、「今どこまで進んでいるか」が見えにくくなります。
この失敗を防ぐには、管理者を明確に立てることと、「報告・連絡・相談」のルールを仕組みとして整えることが有効です。
具体的には:
・各フェーズにおける責任者と判断フローの明確化
・タスク・進捗・課題を一元管理できるツール(例:Backlog、Jira、ClickUp)の導入
・毎週の定例ミーティングに加え、Slackなどのコミュニケーションツールを活用して軽微な進捗共有を習慣化
プロジェクトの規模に関わらず、「小さく、早く、共有する」スタイルを根付かせることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
評価基準が不明確
成果物の評価が曖昧だと、「想定と違う」「頑張ってくれているけど満足できない」といった、もやもやが積み重なります。
これが続くと、発注側・受注側の双方で不信感が生まれ、良好な関係を築くのが難しくなります。評価基準が不明確になりがちな原因は、「何を成功とするか」が言語化・数値化されていないことにあります。
そのため、プロジェクトの開始時点で以下を共有しておくと効果的です:
・品質に関する定量的な目標(バグ件数、テスト通過率など)
・納期や成果物レビューの評価基準
・課題対応や改善提案の頻度・スピードに対する期待値
また、評価を“減点方式”だけで行わず、できたこと・工夫されたことも言語化して伝えることで、関係性の質も向上します。
オフショア開発は、単にコストを外に出すという話ではありません。
信頼できるチームを育てる、リスクを管理する、継続的に成果を上げる——そのための設計と関わり方が、成功の分かれ道になります。
まとめ|オフショア開発の活用は“準備”がカギ
オフショア開発は、コスト削減や人材確保といった目先の課題を解決するだけでなく、中長期的なプロダクト開発体制の強化や、社内リソースの最適化にもつながる有効な手段です。
一方で、距離や文化、言語といった違いがあるからこそ、「任せ方」や「関わり方」によって成果に大きな差が出ることも事実です。
成功のためには、
・パートナー選定の慎重な判断
・要件や期待値の丁寧なすり合わせ
・継続的なコミュニケーションと信頼構築
・管理体制・評価基準・契約まわりの明確化
といった“始める前の準備”と“続けながらの工夫”が欠かせません。
「海外だから難しい」と敬遠するのではなく、「どうすれば伝わるか」「どうすれば活かせるか」を設計できれば、オフショア開発は国内の開発体制を補完・強化する頼れるパートナーになり得ます。
正しい理解と適切な備えがあれば、オフショアは企業の成長を支える“武器”になる——。その可能性を、ぜひ前向きに捉えていただければと思います。
Related column
関連記事
OFFSHORE
アレクシードベトナムの
オフショア開発サービス
約20年のベトナム オフショア開発経験を持つ日系のITソリューションのリーディングカンパニーとして、ソフトウェア開発・システム開発を提供しています。
従来のオフショア開発を進化させた「オフショア開発2.0」により、我々は高品質なオフショア開発を実現します。